『爪から血が出る』原因6つ

ふと愛猫の足元を見たら、爪から血が!こんな光景を目の当たりにしたら驚いてしまいますよね。実は時々、思わぬトラブルから出血することがあるのです。
いざという時に慌てずに対処できるように、そして日頃から防いであげられるように、今回は『爪から血が出る』原因として考えうる要因を6つ紹介いたします。
1.深爪

まず1つ目は、爪を深く切ってしまった際に生じる出血です。そもそも、深爪で血が出てしまうのはなぜなのでしょうか。それには猫の爪の構造が関与しています。
猫の爪をよく観察してみてください。透明な爪の中心部に濃い色の筋のようなものがあるでしょう。これは血管で、血が通っています。
そう、誤って血管をカットしてしまうと血が出てしまうのです。切り込みが深いとそれなりに痛みが出ます。爪切りに対して苦手意識を持つきっかけにもなるので気をつけましょう。
したがって猫の爪を切る際は、この血管の位置を確認し、余裕を持った手前の部分のみ切るようにしてください。
2.巻き爪による食い込み

先ほどのケースは切り過ぎによる出血でしたが、逆に伸びた爪を放置することにもリスクがあります。それが巻き爪による食い込みです。
切ることも研ぐこともなされない爪はただ伸びるだけではなく、重力の影響で段々と巻いた状態になります。そして、最終的に行き着くのが肉球です。鋭利な爪が肉球に刺さることで血が出てしまうのです。
これは相当な痛みを伴う他、傷ついた肉球が炎症を起こし、患部が菌に侵され、そこから感染症へとつながる恐れがあります。
特に寝たきりに近い高齢の猫や、あまり爪を研ぐ習慣のない猫は巻き爪が起こりやすいので要注意です。こまめに爪をカットして、巻き爪自体を防いでいきましょう。
3.爪を引っ張るクセがある(毛繕い編)

猫には毛繕いの日課があります。その過程で肉球を舐め、そのまま爪を引っ張ってしまうことがあります。その結果、爪の血管が傷ついたり、根元から折れて出血する恐れがあるのです。
毛繕いの際に爪を引っ張る猫には次のような特徴があるので、愛猫をよく観察してみてください。
- 几帳面で綺麗好きな性格
- トイレの砂が足に触れることを嫌う
- 長毛種の猫
まず几帳面な性格の猫は毛繕いを熱心に行う傾向にあります。念入りになるあまり、爪のセルフケアを過剰に行ってしまうのです。
被毛の特徴としては、長毛の猫のほうが肉球を気にする傾向があります。理由は足裏にも毛が生えているからです。毛が伸びる過程が気になる、ゴミが詰まりやすいなどの理由から、爪を一緒に引っ張ってしまうことがあるのです。
さらにトイレの砂問題があります。種類としては鉱物系のものを好む猫でも、足裏に砂が挟まることを極端に嫌がる猫がいます。この傾向は長毛種にも当てはまりやすいです。
長毛種の猫に対しては、こまめに足裏の毛をカットしてあげましょう。フローリング滑りによる怪我の予防にも役立ちます。
砂が気になる猫に対しては、砂よけマットを活用してみてください。トイレから出る際にマットを踏むことで砂が取れる仕組みになっています。
几帳面な猫は少し爪が伸びただけでも気になる場合が多いので、こまめにカットすることが予防策につながる可能性があります。
4.爪を引っ張るクセ(ストレス編)

爪を引っ張るクセにはもう1つの傾向があります。それはストレスによる爪噛みのクセです。この場合は、背景に潜む原因を探る必要があります。いくつか例を挙げておくので参考にしてみてください。
- 引越しをした
- 近所で工事が始まった
- 同居動物が増えたもしくは亡くなった
- 飼い主さん側に変化があった
(部署異動・転職・結婚・出産など)
- 猫の愛用品を処分してしまったなど
引越しをする際や模様替えをする際は、愛猫のお気に入りの品はできる限りそのまま残すようにしてください。
そのほかのストレスに関しては、飼い主さんご自身もストレスや疲労を感じている場合が多いでしょう。まずは飼い主さんがリラックスしてください。それだけでも愛猫は安心し、心が落ち着きます。
ストレスによる爪噛みは痛くてもやめられない、もしくはその痛み自体がクセになってしまう、飼い主さんの気を引きたいなど、コントロールが難しいケースが多いです。
早めに心の痛みに気づいてあげられるように、そしてストレスを溜め込まないようにケアをしてあげてくださいね。
5.ケガによる爪の破損

日頃からカーテンによじ登る、よく走り回る、キャットタワーに乗る猫は、思いがけず爪が折れて血が出てしまう場合があります。
このケガによる爪の破損はこまめに爪をカットすることで防ぐことができます。
6.外傷以外の病気

これまでのケースに当てはまらない場合は、"外傷以外の病気"が背景にあるかもしれません。爪からの出血を伴う病気をいくつか挙げてみます。
- 爪周囲炎
- 血液の凝固異常
- 全身性疾患
- 腫瘍など
爪周囲炎は、先ほどの巻き爪がきっかけでも起こる可能性があるので詳しく紹介いたします。
爪周囲炎とは、爪やその周辺の皮膚に細菌やカビが侵入することで引き起こされる炎症及び感染症です。症状は出血の他、爪の付け根が赤く腫れる、膿や独特のにおいを放つなどが見られ、痛みを伴います。
巻き爪が引き金となるケースでは、爪が食い込んだ先の肉球が炎症を起こし、感染症へと発展します。
いずれの場合も、爪周囲炎が自然治癒することはあまり期待できません。異変に気づき次第、動物病院で診察を受けてください。
爪から血が出たときの応急処置と対処法
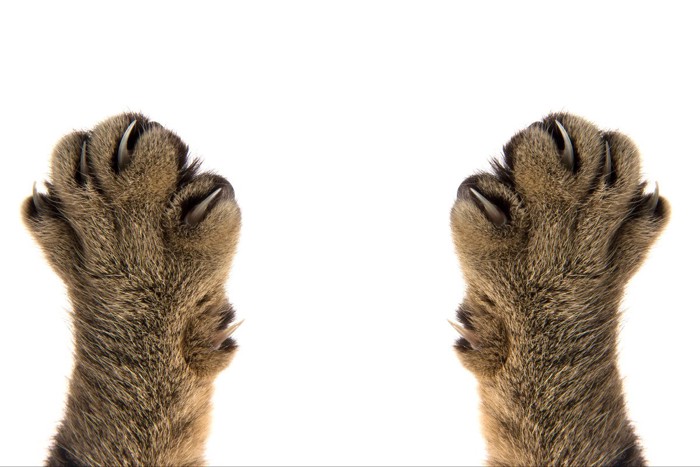
愛猫の爪から血が出ているのを見つけると、飼い主さんも驚いてしまいます。しかし、落ち着いて適切に対処すれば多くの場合は大きな問題に発展しません。
ここでは、緊急時に取るべき基本的な手順を順を追って解説します。
1.出血源と状態の確認
まずは どの爪から出血しているのか を確認し、周囲の状態をよく観察しましょう。
- どの爪が出血しているか
- 爪が折れていないか(ヒビ欠けなどもチェック)
- 出血量は多くないか
短時間で判断することが大切です。爪が完全に折れていたり、根元が大きく損傷している場合は深刻なケースもあるため、早めの受診が必要になります。
2. ぬるま湯で洗浄
出血量が少ない場合は、まずぬるま湯で優しく洗い流して清潔にすることが基本です。
洗浄することで、以下のメリットがあります。
- 汚れや細菌を落として感染を予防
- 出血の程度をより正確に確認できる
このとき、人間用の消毒液(アルコール・ヨードなど)は刺激が強く、かえって痛みや舐めた際の中毒リスクがあるため絶対に使用しないでください。
3. 出血が続く場合は止血
洗浄後も出血が続くようなら、 清潔なガーゼやティッシュで軽く圧迫してください。強く押しつける必要はなく、軽い圧で5〜10分を目安に止血します。
10分ほどで血が止まり歩き方に異常がない、痛がる様子がないようであれば、数日間は自宅で様子を見るだけで問題ないケースがほとんどです。
4. 受診が必要なケース
次のような場合は、 自宅での対処だけでは危険な可能性があるため受診が必要です。
- 出血量が明らかに多い
- 10分以上押さえても血が止まらない
- 歩き方が不自然(足を浮かせる、引きずる)
- 触ると強い痛みで激しく嫌がる、鳴く
- 爪が根元から折れているように見える
- 爪周りが腫れている、膿のようなものがある
これらは 爪周囲炎や骨・爪床の損傷 の可能性もあり、早期治療が必要になります。まずは電話で動物病院に状況を伝え、指示を仰ぎましょう。
日頃のケアが最大の予防
爪のトラブルの多くは、深爪や巻き爪、爪の欠け・折れなど、日常的なお手入れで防げるものばかりです。
しかし、猫の性格や体格によっては、家庭での爪切りが難しい場合もあります。無理はせず、うまくできないと感じたら獣医師やトリマーに相談するのも安全な選択肢です。
まとめ

猫の爪からの出血は、深爪や巻き爪、クセによる引っ張り、ケガ、さらには病気まで、さまざまな要因で起こりえます。いずれのケースでも、早期に気づいて適切に対処することが大切です。
自宅でできる応急処置は限られていますが、落ち着いて確認・洗浄・止血の手順を踏めば、ほとんどは大きなトラブルに発展せずに済みます。一方で、出血が多い、痛がる、腫れている、折れているなどの異変がある場合は、迷わず動物病院へ相談してください。
そして何より大切なのは 日頃のケア です。適切なタイミングで爪切りをすること、足裏の毛を整えること、ストレスを溜めさせないことなど、毎日の積み重ねがトラブルの予防につながります。
愛猫がいつも通り快適に歩き回り、安心して過ごせるように、ぜひ今回紹介したポイントを参考にしながら、普段から爪の状態をチェックしてあげてくださいね。


