猫の脳と知能のレベル
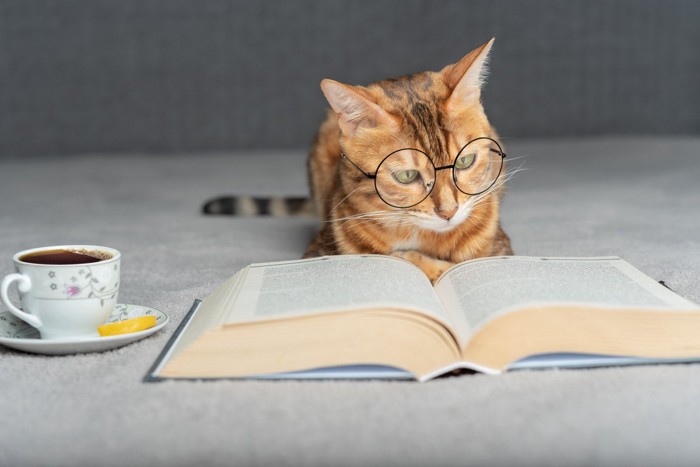
猫の脳は30gと言われており、人間の脳が1200~1500gであることと比較するととても小さいと言えます。ただし、大脳皮質の構造や神経細胞の配置は人間とほぼ変わらず、知覚・思考・記憶に関わる領域もしっかり発達しています。
とはいえ、猫には心理学的なテストを実施できないため、厳密な知能指数(IQ値)を算出することはできません。そのため、猫の知能は一般的に行動観察によって調べられています。その結果、猫は「人間の2〜3歳児ほどの知能」を持っているだろうといわれています。これは、簡単なパターンの認識と記憶、問題解決ができるレベルです。
実際に猫は自分の名前を理解し、呼んだら返事をして近づいてきたり、飼い主の行動パターンを学習して、状況に応じて行動を変えたりすることが可能です。また、感情表現も幼児並みに多様です。
猫と他の動物との比較

猫の知能レベルは人間の2〜3歳児程度だとわかりましたが、他の動物と比べるとどうなのでしょうか。それぞれの動物が持つ知能のタイプの違いにも注目して比較してみましょう。
猫と犬の知能の違い
犬は人間に飼われてきた歴史が長く、牧羊犬や猟犬、盲導犬など、さまざまな犬種が作られてきました。中でも、人間の指示をよく理解して従う賢い個体が優先的に繁殖に選ばれてきたため、世代を重ねるごとに「人と協力し合う」という社会的知能が高くなってきたのです。
一方、猫は人間の集落の周りで生きてきたものの、単独で暮らしていたので、問題を自分で考えて判断し、行動に移すことが得意です。そのため猫は「ひとりでなんとか物事を解決する」という能力に優れているのです。
サルやイルカなど知能が高い動物との比較
「抽象的思考」とは、目に見えない概念や因果関係を理解して、直接経験していない情報をもとに推論や計画を立てる能力です。
サルやイルカでは、この抽象的思考の発達が、道具を使う行動や仲間との協力行動に表れます。サルは道具を使うだけでなく、必要な時にはその道具を改変することもできます。また、イルカは仲間と役割分担をして状況に応じて戦略まで変更し、魚の群れを追い込む狩りをするのです。
一方、猫は経験に基づいた「具体的思考」という実用的な知能が中心です。これは単純な因果関係の理解、つまり飼い主が棚を開けたら食事の出るタイミングだと覚えたり、ドアノブを下に降ろせばドアが開くと覚える行動です。逆に、複雑な道具を使ったり、同居猫と役割分担をして柔軟に行動するなど、推論や計画を伴う行動は苦手です。
猫の能力が優れているところ

猫は長い間、単独で生活してきたことが、現在の優れた能力につながっています。そのひとつが、自分で考え、判断し、行動するという独立した問題解決能力です。
猫は複雑な仮説を立てることは得意ではありません。1〜2工程ほどの短い流れであれば理解できますが、目の前の出来事を経験として学び取り、解決する力の方が優れています。たとえば、食事の時間を覚えて催促したり、飼い主の動きを観察してドアの開け方を真似したりする行動がその例です。
もうひとつが、周囲の状況や相手の反応を敏感に察知して行動する安全性を見極める能力です。猫は安全な場所や心地よい環境、嫌な音などを正確に記憶し、危険の少ない快適な居場所を見つけます。さらに、人間の声のトーンや表情から感情を読み取り、相手の状態に合わせて行動を変える柔軟さも備えています。
こうした感覚的で繊細な知性は、単独で生きてきた猫が環境に適応しながら培ってきた生存の知恵といえるでしょう。
まとめ

猫の知能は、理屈で考えるよりも直感で動くのが得意です。そのため、あれこれ教えるよりも、猫が自分で考えて行動できるように見守ることが大切です。
もし、愛猫の持つ能力を発揮させてあげたい、伸ばしてあげたいと感じるなら、ふだんの遊びを通して脳を刺激することが効果的です。ただ遊ぶだけでなく考えたり工夫したりする要素がある知育玩具などを使い、考えながら遊ばせるようにしましょう。
ただし、同じ遊びを繰り返したり、おもちゃをそのままにしておくと、すぐに慣れて飽きてしまいます。クリアできるとわかれば刺激も薄れるため、遊びの後は片づける、少しずつ変化を加えるといった工夫で刺激を保つことが大切です。


