︎膵炎とは
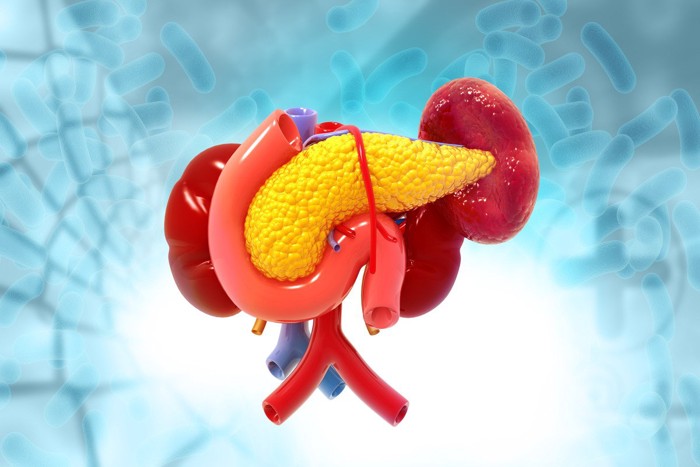
膵炎とは膵臓から出る消化酵素が何らかの理由で活性化してしまい、膵臓に炎症が起こる状態のことを指します。
膵炎には短期間に急激に症状が悪化する急性膵炎と、症状が比較的分かりにくく長期間かけて発症する慢性膵炎とがあります。
犬と違い、猫では慢性膵炎が多いと言われています。
︎症状

慢性膵炎では、元気消失、脱水、下痢、嘔吐、腹痛、食欲不振、体重減少などがみられます。しかし、この全ての症状が現れる事は少なく、いずれか一つのみという場合も多くあります。
何となくいつもよりも元気がない、時々吐く頻度が多いなど、あまり特徴的ではっきりとした症状が現れない事が多いです。そのため早期に膵炎だと気がつけない事が多く、診断されるまで長い間膵炎を患っている猫も少なくありません。
猫ではあまりみられないですが、急性膵炎では激しい嘔吐、激しい腹痛、食事や水分が全く取れなくなるなど、急激な症状を示します。急性膵炎は、膵臓だけでなく他の臓器に炎症が広がる事で数日以内に亡くなってしまう事もある怖い病気です。
︎検査法

軽い胃腸炎のような症状が続いており、消化器症状に対する薬を飲んでも改善しない場合、膵炎を疑って血液検査をする必要があります。
膵炎の検査はSpec fPL(猫膵特異的リパーゼ)という血液検査の項目を測定する事で値が基準値より高いと、膵炎だと確定診断する事ができます。この検査項目は一般的な血液検査には含まれておらず、動物病院で行われた一般的な血液検査が正常だから膵炎でないとは言えません。
飼い猫が膵炎かもしれないと思った飼い主さんは、膵炎の検査をしてほしいと獣医師に伝えましょう。
︎治療法

急性膵炎の場合では、急激な症状の悪化が見られるため、静脈から点滴を流し、食事が摂れない場合には、鼻カテーテルや食道チューブから強制的に食事を与えるなど、入院での治療が必要となります。
慢性膵炎の場合は、全く食事が摂れなくなるという事は少ないため、基本的には自宅での管理となります。
膵臓に炎症を起こす原因となっているタンパク分解酵素が、膵臓に働かないようにするための阻害薬を内服します。また、吐き気止めや痛み止めなど症状に合わせた注射薬や内服薬で治療する事が多いです。
︎予防法

猫の膵炎は原因不明な事が多いため完全な予防は難しいですが工夫次第でそのリスクを下げる事はできます。
まずは適切な体重管理をする事が大切です。極端な肥満は膵臓に負担をかけるとされているため、定期的に体重を測り肥満を予防しましょう。
また、極端な高脂肪の食事は膵臓に負担がかかります。人のご飯などを大量にあげるなど、膵臓や胃腸に負担のかかる食事は避けるようにしましょう。
そして稀ですが、猫では大腸菌などの細菌感染や、猫伝染性腹膜炎、ウイルス性鼻気管炎などのウイルス感染、トキソプラズマなどの原虫感染によって、膵炎が起こる場合があります。
これらへの感染を防ぐためにも、不清潔な食べ物や水は避ける、混合ワクチンを接種する、生肉を与えない、外に出してネズミなどの狩りをさせない事が予防になります。
︎まとめ

猫の膵炎は症状があいまいな事が多くただの胃腸炎として治療されてしまい、膵炎が長期間放置されてしまう事があります。
膵炎は長期化すると糖尿病のリスクにも繋がるためなるべく早期に治療を開始する事が大切です。
いつもよりも少し嘔吐の頻度が高い、少し食欲が落ちたなど、小さな異変も見逃さないようにしましょう。
そして消化器症状が改善されない場合には獣医師に膵炎の検査を飼い主さんから依頼できる事も覚えておきましょう。


